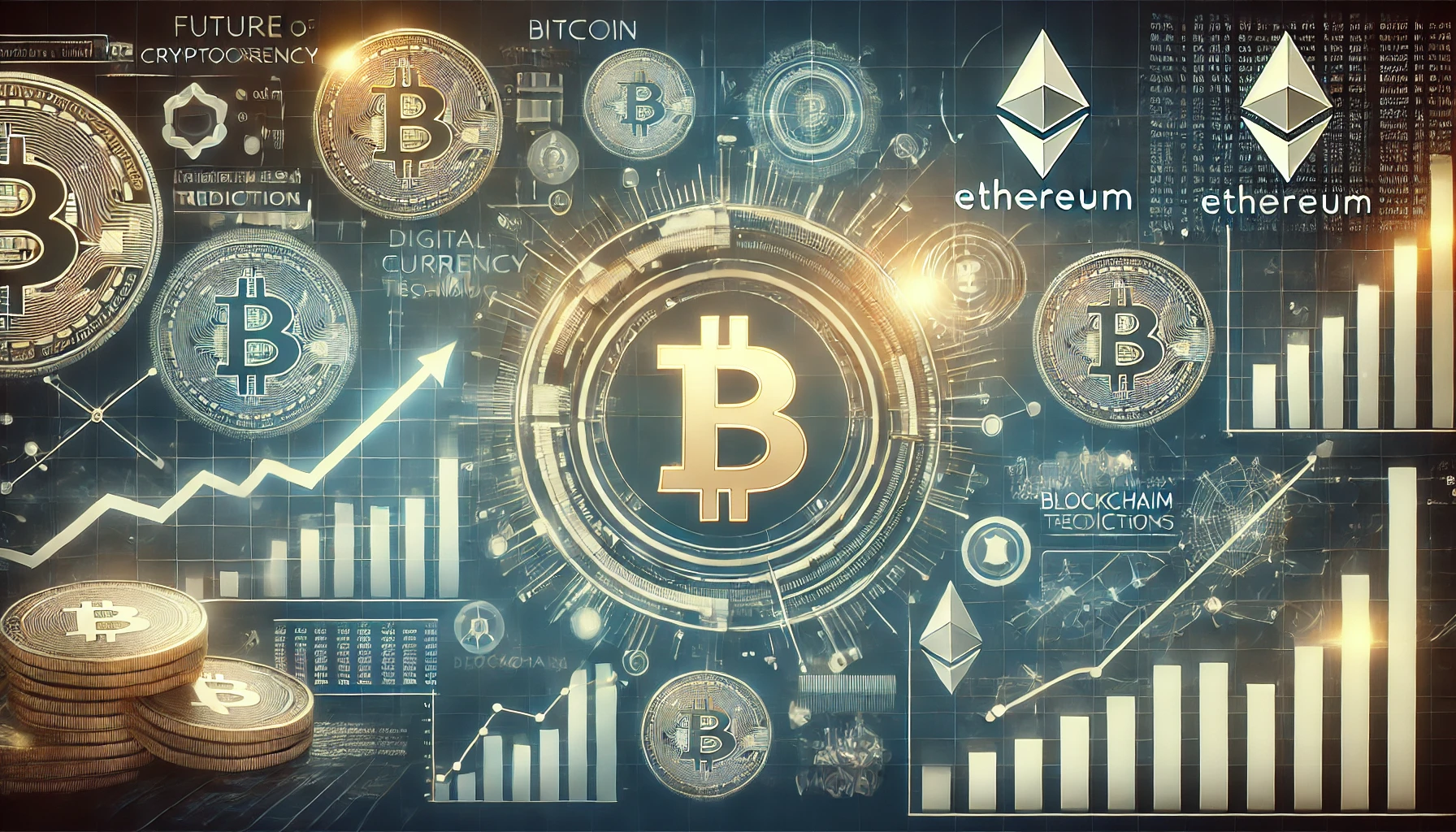はじめに
仮想通貨(暗号資産)の世界は日進月歩であり、日々多くの技術革新や新しいプロジェクトが誕生しています。そのため、初心者から上級者まで、常に最新動向を追いかけなければいけません。しかし、新しい概念が次々に出てくると「そもそもこの用語はどういう意味だろう?」と疑問を持つことも多いはずです。
本記事では、仮想通貨やブロックチェーンに関係する重要なキーワードをまとめ、簡潔な解説を添えています。あるキーワードを理解したうえで、さらに深堀りしたい用語が出てきたら、この用語集の中や他の情報源を参照し、理解を深めていただくことを目的としています。
読み方のわからない英語の専門用語や省略形、あるいは複雑なテクノロジー関連の言葉などを「ざっと把握したい」ときにお役立てください。これをきっかけに仮想通貨の世界観を理解し、最新技術や投資判断に役立てていただければと思います。
1. 仮想通貨(Cryptocurrency)
解説
「仮想通貨」は、インターネット上でやり取りされるデジタル資産の総称です。ブロックチェーン技術を用いて取引の正当性や信頼性を確保しているものが多く、代表例としてビットコインやイーサリアムなどがあります。政府や中央銀行といった特定の管理者を持たず、分散的に管理される点が特徴です。日本では、金融庁の呼称で「暗号資産」とされることもあります。
2. 暗号資産(Crypto Asset)
解説
日本における法令上の正式な呼び方が「暗号資産」です。世界的には「Cryptocurrency」「Digital Asset」「Virtual Currency」などさまざまな呼称があり、法規制や地域によっても言い方が異なります。日本の金融庁は「暗号資産」の文言を使うことで、仮想通貨が資金決済手段として利用されるだけでなく、多様な活用法やその性質を持つデジタル資産であることを明確にしています。
3. ブロックチェーン(Blockchain)
解説
ブロックチェーンは分散型台帳技術の一種で、取引情報を「ブロック」ごとにまとめ、それをチェーンのようにつなげる形で記録する仕組みです。過去のデータを改ざんするのが非常に難しく、中央管理者を必要としない点が画期的です。ビットコインの登場によって広く知られるようになり、現在では金融以外の分野にも応用が検討・実装されています。
4. ビットコイン(Bitcoin / BTC)
解説
2009年に運用が開始された世界初の分散型デジタル通貨です。サトシ・ナカモト(Satoshi Nakamoto)という謎の開発者(または集団)が発表したホワイトペーパーを元に開発されました。中央管理者が存在せず、マイニング(採掘)と呼ばれる仕組みによって新たなビットコインが発行され、ブロックチェーン上にすべての取引が記録されます。仮想通貨の代名詞的存在です。
5. イーサリアム(Ethereum / ETH)
解説
ビットコインに次ぐ時価総額を持つ主要なブロックチェーンプラットフォームの一つです。単なる通貨機能だけでなく、スマートコントラクトと呼ばれる自動契約機能を搭載していることが特徴となっています。これにより、分散型アプリケーション(DApps)を構築する土台として幅広く利用されています。ネイティブトークンが「ETH(イーサ)」です。
6. スマートコントラクト(Smart Contract)
解説
あらかじめプログラムされた条件が満たされると、自動的に契約を実行する技術のことを指します。契約書の内容をコード化し、ブロックチェーン上で管理することで、第三者なしでも公正にやりとりや手続きを実行できるのが特徴です。イーサリアムはスマートコントラクトの概念を広めたプロジェクトとして特に有名です。
7. マイニング(Mining)
解説
ビットコインなどPoW(Proof of Work)を採用しているブロックチェーンで、新たな取引を検証し、正しいブロックを作るために計算作業を行うことを指します。その報酬として、新規発行される仮想通貨や取引手数料がマイナー(マイニングを行う人・組織)に支払われます。高性能なマイニング専用機器が必要になり、大量の電力を消費するケースが多いことも問題となっています。
8. ハッシュレート(Hash Rate)
解説
マイニングの過程で、暗号学的ハッシュを計算する速度のことを指します。ハッシュレートが高いほど、一秒間に多くの計算を行えるため、ブロックを生成する競争(マイニング)において優位になります。ネットワーク全体のハッシュレートが高いほど、ブロックチェーンの安全性(51%攻撃などのリスク回避)も高まるとされています。
9. ハッシュ(Hash)
解説
データを一定の長さの文字列に変換する関数(ハッシュ関数)や、その結果得られる固定長の値を指します。ブロックチェーンでは取引データをまとめてハッシュ化し、ブロックに記録することでデータの改ざんが極めて難しくなります。代表的なハッシュ関数として「SHA-256」などがあります。
10. 51%攻撃(51% Attack)
解説
ブロックチェーンネットワークの合意形成において、悪意ある参加者がネットワークの過半数(51%以上)のハッシュレートやステークを掌握することで、取引の改ざんや二重支払いを引き起こす攻撃手法です。これが実行されるとブロックチェーンの信頼性が大きく損なわれるため、ネットワークの分散性とハッシュレートの高さが重要とされます。
11. ウォレット(Wallet)
解説
仮想通貨を保管・管理し、送受金を行うためのソフトウェアまたはハードウェアのことです。ビットコインなどの仮想通貨は実際に「ウォレットの中」にあるのではなく、ブロックチェーン上に記録されています。ウォレットはその通貨を操作するのに必要な秘密鍵を管理し、安全に取引を行えるようにする役割があります。オンライン型、オフライン型、ハードウェアウォレットなどさまざまな形態が存在します。
12. 秘密鍵(Private Key)
解説
仮想通貨ウォレットにおいて、資産を使用する際に必要となる鍵(文字列)のことです。秘密鍵を使ってブロックチェーン上の取引に署名することで、自分がそのコインを動かす正当な権利者であると証明します。秘密鍵が漏洩・紛失すると資産を失う可能性があるため、厳重な管理が求められます。
13. 公開鍵(Public Key)
解説
秘密鍵から導き出されるペアとなる鍵です。秘密鍵は非公開ですが、公開鍵は第三者に知られても安全性が担保されるように暗号技術が設計されています。公開鍵からさらにウォレットアドレスなどを生成し、他者との取引に用いることができます。公開鍵暗号の仕組みによって、第三者は公開鍵を使い取引の正当性を検証できます。
14. ウォレットアドレス(Address)
解説
仮想通貨を受け取る際に使われる文字列です。ビットコインの場合は「1」や「3」あるいは「bc1」などで始まる30数文字の英数字列が典型的です。イーサリアムでは「0x」で始まる場合が多いなど、ブロックチェーンや通貨の種類によって異なる形式が存在します。公開しても問題ない情報ですが、秘密鍵とセットで管理することで取引が成立します。
15. 取引所(Exchange)
解説
仮想通貨の売買を仲介するサービスやプラットフォームのことを指します。ユーザーは法定通貨(日本円、米ドルなど)や別の仮想通貨と交換でき、口座開設が必要な中央集権型取引所(CEX)と、ウォレットを介して直接取引する分散型取引所(DEX)があります。手数料や対応通貨、使いやすさなどが異なるため、利用目的に応じた選択が重要です。
16. 中央集権型取引所(CEX: Centralized Exchange)
解説
企業や特定の管理者が運営し、ユーザーが口座を開設して利用する取引所です。資金を取引所に預け入れて売買を行う仕組みで、使いやすいUI/UXや高い流動性が得られる反面、取引所がハッキングされたり経営破綻した場合に資金が失われるリスクがあります。例としてBinanceやCoinbase、国内ではbitFlyerやCoincheckなどが挙げられます。
17. 分散型取引所(DEX: Decentralized Exchange)
解説
中央管理者を介さず、ブロックチェーン上のスマートコントラクトによって売買が行われる取引所のことです。ユーザーは自分のウォレットを接続して取引し、資産を自分自身で管理しながら売買できるため、ハッキングリスクが相対的に低いとされています。しかし、流動性や使い勝手、取引手数料の高さが課題となるケースもあります。代表例としてUniswapやSushiswapなどがあります。
18. DApps(分散型アプリケーション)
解説
中央集権的サーバーではなく、ブロックチェーンなど分散型ネットワーク上で動作するアプリケーションの総称です。バックエンドのロジックをスマートコントラクトが担うため、検閲耐性や透明性が高い点が特徴です。ゲームやSNS、ファイナンスなど多岐にわたるユースケースが存在し、DeFiやNFTの分野と合わせて注目を集めています。
19. DeFi(分散型金融:Decentralized Finance)
解説
金融機能(貸し借り・資産運用・保険など)をブロックチェーン上のスマートコントラクトによって分散的に実現する仕組みを指します。中央機関を介さずにユーザー同士で金融サービスを利用できる点が画期的で、代表例としては「Uniswap」のAMM(自動マーケットメイカー)や「Aave」「Compound」のレンディングなどがあります。
20. NFT(Non-Fungible Token)
解説
非代替性トークンと呼ばれ、唯一無二のデジタル資産を表すトークンのことです。ブロックチェーン上で発行されるため、所有権や希少性、真正性を証明しやすいという特徴を持ちます。アート作品、ゲームアイテム、デジタルコンテンツなど多様な分野で活用されており、近年は高額で取引されるケースも珍しくありません。
21. ERC-20
解説
イーサリアム上で発行されるトークンの共通規格の一つで、主に**可換性(Fungible)**を持つトークンを対象とします。ICOやトークン販売などで多く使用されており、ウォレットや取引所での互換性が保たれやすいように、トークンの基本的な振る舞いを標準化しています。最も普及しているトークン規格です。
22. ERC-721
解説
イーサリアム上で非代替性(Non-Fungible)を備えたトークンを実装するための規格です。NFTの代表的な規格であり、一意のIDを持ち、それぞれのトークンが互いに代替不可能であることを証明できます。アートやゲームアイテムなど、ユニークなデジタル資産の取り扱いに適しています。
23. ERC-1155
解説
ERC-721とERC-20の両方の特性を兼ね備えた柔軟なトークン規格です。単一のコントラクトで複数のトークンを管理でき、代替性のあるトークン(Fungible)と非代替性のあるトークン(Non-Fungible)を混在して扱うことが可能です。ゲーム開発や複数種類のデジタル資産管理に便利な設計となっています。
24. ガス代(Gas Fee / Transaction Fee)
解説
イーサリアムやその他のブロックチェーンでトランザクションを実行する際に支払われる手数料のことです。ノードを運営するマイナーや、Proof of Stakeではバリデーターに報酬として支払われることで、ネットワークの安全性と維持に寄与します。ネットワークの混雑時にはガス代が高騰することもあり、利用者の悩みの種です。
25. ガスリミット(Gas Limit)
解説
イーサリアムのトランザクションを送る際に、処理にかけられる最大量のガス(手数料の上限)を指定する値です。複雑なスマートコントラクトの実行には多くのガスを消費するため、十分なガスリミットを設定しないと処理が失敗することがあります。一方、設定が高すぎると過剰な支払いになる可能性もあるため、適切な設定が求められます。
26. コンセンサスアルゴリズム(Consensus Algorithm)
解説
ブロックチェーンにおける参加者全員が、どのようにして「正しい取引データ」を合意し、台帳を更新していくかという仕組みのことです。代表的なアルゴリズムには「Proof of Work(PoW)」と「Proof of Stake(PoS)」があり、他にも「DPoS」や「PBFT」、チェーン同士での合意を行う独自方式など、さまざまな手法が研究されています。
27. Proof of Work(PoW)
解説
ビットコインが採用しているコンセンサスアルゴリズムで、大量の計算を行い正解を見つけることでブロックを生成する仕組みです。計算力に応じてブロック報酬を得られるため、公平性がある一方で、膨大な電力消費や専用マイニング装置のコストが問題視されています。
28. Proof of Stake(PoS)
解説
保有している仮想通貨(ステーク)の量や期間に応じて、ブロック生成の確率が上がる仕組みを採用するコンセンサスアルゴリズムです。PoWのように大量の計算は不要で、環境負荷の低減が期待されます。イーサリアムも2022年の「The Merge」によってPoWからPoSに移行し、電力消費が大幅に抑えられました。
29. ステーキング(Staking)
解説
PoSを採用するブロックチェーンで、自分の保有する仮想通貨をロック(預け入れ)することで、ネットワークのバリデーションに参加し、その報酬として追加のトークンを得る仕組みです。銀行の定期預金のような感覚で運用が可能な場合もあり、個人投資家から機関投資家まで幅広く注目を集めています。
30. バリデーター(Validator)
解説
ブロックチェーン上で取引を検証・承認し、新たなブロックを提案する役割を担うノードのことです。PoS系のチェーンではコインのステークを条件に、この役割を担うことができます。バリデーターとして稼働するためには、ネットワークの指定する最低ステーク量や稼働環境などの要件を満たす必要があります。
31. DPoS(Delegated Proof of Stake)
解説
ステークの委任型コンセンサスアルゴリズムで、ホルダーは自分の保有するコインを信頼するバリデーターに委任し、そのバリデーターがブロック生成を行う仕組みです。投票制によりバリデーターが選出され、透明性や民主的なガバナンスを目指すブロックチェーンが多く採用しています。EOSやTRONなどで採用されています。
32. TPS(Transactions Per Second)
解説
1秒あたりに処理できるトランザクション数を表す指標です。クレジットカード決済システムなどに比べ、ビットコインやイーサリアムのTPSは低いと言われてきました。スケーラビリティの問題を解決するため、各ブロックチェーンプロジェクトがTPSの向上を目指して研究・開発を進めています。
33. スケーラビリティ(Scalability)
解説
ブロックチェーンのトランザクション処理能力が、ユーザーや取引量の増加に対応できるかどうかを示す概念です。中央集権的システムに比べると分散型システムは処理が遅くなりがちで、手数料の高騰や遅延が起こることがあります。代表的なスケーリング手法には「オンチェーンの拡張(シャーディング)」や「オフチェーンソリューション(サイドチェーンやレイヤー2)」などがあります。
34. レイヤー2(Layer 2)
解説
メインのブロックチェーン(レイヤー1)の外または上に構築されるソリューションを指し、トランザクション処理を一部肩代わりすることで本体チェーンの負荷を軽減します。代表的な例としてはイーサリアムの「Optimistic Rollup」「ZK Rollup」、ビットコインの「Lightning Network」などが挙げられます。スケーラビリティと低コスト化を実現する方法として期待されています。
35. Lightning Network(ライトニングネットワーク)
解説
ビットコインのオフチェーン決済プロトコルの一種で、小額決済を高速かつ低手数料で行うことを目指して開発されました。ユーザー同士がチャネルを開設し、そのチャネル内で複数回のやり取りを行って最終結果だけをビットコインのブロックチェーンに書き込みます。これによってメインチェーンの混雑を緩和し、高速決済を可能にします。
36. シャーディング(Sharding)
解説
ブロックチェーンを複数のセクション(シャード)に分割し、それぞれ並行して取引を処理することで全体の処理能力を高める手法です。データベースの世界では一般的な技術ですが、分散型台帳に適用するのは難易度が高いとされています。イーサリアム2.0(現PoSイーサリアム)の計画の一部として実装が予定されています。
37. メタマスク(MetaMask)
解説
イーサリアムなどEVM互換チェーン向けのブラウザ拡張型ウォレットの一つです。ChromeやFirefoxなどのブラウザにインストールして使い、DAppsとの連携が容易であることから世界的に広く利用されています。秘密鍵はローカルに保存されるため、取引所に資産を預けずに自分で管理したいユーザーにとって便利な選択肢です。
38. ハードウェアウォレット(Hardware Wallet)
解説
秘密鍵をオフラインで保管する専用デバイスで、USB接続などを介して使用します。代表的な製品としてLedgerやTrezorがあります。オンライン環境に常に晒されないため、ハッキングリスクが低く安全性が高いとされていますが、デバイスの紛失・破損には注意が必要です。
39. KYC(Know Your Customer)
解説
金融機関や取引所が、マネーロンダリングやテロ資金供与などを防ぐために顧客の身元確認を行う手続きを指します。本人確認書類の提出や住所証明などが含まれます。中央集権型の仮想通貨取引所ではアカウント開設時にKYCが必須であることが一般的ですが、分散型取引所(DEX)ではKYCを要求しないケースもあります。
40. AML(Anti-Money Laundering)
解説
マネーロンダリング(資金洗浄)を防止するための施策や法規制の総称です。KYCとともに金融機関や取引所にとっては重要なコンプライアンス項目であり、不正取引の監視や報告が求められます。国や地域によって法規制の度合いは異なり、仮想通貨業界でも規制強化が進んでいます。
41. ホワイトペーパー(White Paper)
解説
仮想通貨やブロックチェーンプロジェクトが、その技術的背景や目的、設計などをまとめて公開する文書のことです。ビットコインのホワイトペーパーをはじめ、多くのプロジェクトがホワイトペーパーを基礎資料として発表し、投資家やコミュニティの理解を得る手段となっています。投資判断にも重要な資料です。
42. ICO(Initial Coin Offering)
解説
ブロックチェーンプロジェクトが資金調達を目的に、独自のトークンを販売する行為を指します。2017年頃に大きく注目され、多数のプロジェクトがICOを実施しました。しかし詐欺まがいのケースも多発し、各国の規制が強化された経緯があります。最近はSTO(Security Token Offering)など、より法的整備がされた形態も登場しています。
43. STO(Security Token Offering)
解説
証券扱いのトークンを発行して行う資金調達方法です。トークンの所有者に配当や議決権などの権利が付与されるため、既存の株式や債券などに近い側面があります。証券法に則った手続きが必要で、ホワイトリスト登録など厳格な制度設計を行うプロジェクトが増えています。ICOに比べて投資家保護が強化されている場合が多いです。
44. IEO(Initial Exchange Offering)
解説
仮想通貨取引所が主体となって実施されるトークンセールの形式です。取引所側がプロジェクトの審査を行い、一定の基準を満たしたプロジェクトのみを上場・販売するため、投資家にとってはICOよりも安全性・信頼性が高いとされています。BinanceやHuobiなど大手取引所が積極的に実施しているケースがあります。
45. ホワイトリスト(Whitelist)
解説
特定のプロジェクトやアドレスを事前に承認し、優先的に販売や配布を受けられる権利、もしくはその管理リストのことです。NFTの販売前やIEO/ICOの際に、早期コミュニティメンバーや当選者を「ホワイトリスト」に登録して先行購入権を与えるような施策がよく行われます。参加者にとっては有利な条件を得られることがあります。
46. カストディ/ノンカストディ(Custody / Non-Custody)
解説
仮想通貨において、カストディウォレットは秘密鍵を第三者(取引所やカストディ業者)が保管するタイプ、ノンカストディウォレットはユーザー自身が秘密鍵を管理するタイプを指します。カストディでは使いやすさやパスワードリカバリーが期待できますが、ハッキングや倒産リスクもあります。ノンカストディでは資産を自分で管理できる一方、秘密鍵紛失時のリスクも自己責任です。
47. ガバナンストークン(Governance Token)
解説
プロジェクトやプロトコルの運営方針や意思決定に投票権を持つトークンのことです。DeFiの分散型プロトコルやDAOなどで採用され、トークン保有者は提案への賛否を投票することでプロジェクトの方向性を左右します。メジャーな例としてはUniswapのUNI、CompoundのCOMPなどがあります。
48. DAO(Decentralized Autonomous Organization)
解説
ブロックチェーン技術を活用して、中央管理者なしで組織運営や意思決定を行う仕組みを指します。参加者はガバナンストークンやスマートコントラクトを通じて投票権を行使し、透明性の高い形で組織を運営します。DAOによって資金調達、投資、報酬分配などが分散的に行われるため、新たな組織形態として注目を集めています。
49. イールドファーミング(Yield Farming)
解説
DeFiプロジェクトに仮想通貨を預け入れることで、流動性提供の見返りやステーキング報酬、貸し出し金利などから収益を得る行為を総称して指します。複数のプロトコルを組み合わせてより高い収益を狙うユーザーも多く、DeFiブームを支える要因の一つとなりました。ただし、リスク管理が難しい場合も多く、注意が必要です。
50. インパーマネントロス(Impermanent Loss)
解説
自動マーケットメイカー(AMM)形式の分散型取引所に流動性提供した際、預けたトークンの価格変動によって発生する「確定していない損失」を指します。価格変動が大きいと、プール内の資産配分が変わり、結果的にトークンを保有していた場合よりも不利になることがあります。流動性提供の報酬と比較して、損益を総合的に判断する必要があります。
51. AMM(Automated Market Maker)
解説
伝統的なオーダーブック方式ではなく、プールされた流動性に対して自動的に価格を算定する仕組みです。UniswapやSushiSwapなどが代表例で、ユーザーはトークンをプールに預け流動性提供し、その見返りに手数料を得ます。一方、インパーマネントロスなどのリスクが伴う点も理解しておく必要があります。
52. レンディング(Lending)
解説
仮想通貨を預け入れて貸し出し利息を得たり、逆に仮想通貨を担保に資金を借りたりする行為です。中央集権型のレンディングサービスでは企業が運営を行いますが、DeFiではスマートコントラクトが仲介し、自動的に利率の算出や担保管理を行います。AaveやCompoundなどが代表的なプラットフォームです。
53. フラッシュローン(Flash Loan)
解説
DeFi特有の仕組みで、担保なしでも瞬間的に大きな金額を借り入れできるローンです。同一トランザクション内で借り入れから返済までが完結しない場合は自動的にキャンセルされるため、貸し手にとってリスクが少ないのが特徴。一方でフラッシュローンを悪用した攻撃(価格操作など)も問題となっています。
54. クロスチェーン(Cross-Chain)
解説
異なるブロックチェーン同士でデータや資産の移転を可能にする技術やプロトコルのことです。ビットコインとイーサリアム、あるいは他のレイヤー1同士など、相互運用性(Interoperability)の向上が期待されています。代表例として、PolkadotやCosmosなどがクロスチェーンを念頭に置いた設計を進めています。
55. ラップドトークン(Wrapped Token)
解説
あるブロックチェーン上の資産を、別のブロックチェーンで表現・取引できるようにパッケージしたトークンです。例えば、ビットコインをイーサリアム上でトークン化した「WBTC(Wrapped Bitcoin)」などが代表例。これにより、異なるチェーン間での流動性が高まり、DeFiなど多彩なユースケースで利用が可能になります。
56. マルチシグ(Multi-Signature / MultiSig)
解説
複数の秘密鍵が揃わないと取引に署名できないようにする仕組みです。複数人で資産を管理するときや、ウォレットへのハッキングリスクを分散させる目的で活用されます。例えば、3/5マルチシグでは5つの鍵のうち3つが揃わないと送金が実行されません。企業やDAOなどでセキュリティ強化策としてよく使われます。
57. ハードフォーク(Hard Fork)
解説
ブロックチェーンのルール(プロトコル)を大幅に変更する際に発生し、旧バージョンとの互換性が失われる分岐のことです。新旧チェーンが同時に存在し、トークンが2つに分裂する場合もあります。ビットコインキャッシュ(BCH)はビットコインからのハードフォークによって誕生し、イーサリアムクラシック(ETC)もDAOハック事件後に発生したハードフォークの結果として存在しています。
58. ソフトフォーク(Soft Fork)
解説
既存のブロックチェーンと後方互換性を保つ形で行うアップグレードです。新しい機能が追加された場合でも、旧バージョンのノードはアップグレード後のブロックを検証できます。ビットコインのSegWit(セグウィット)などが代表例で、ハードフォークに比べてコミュニティの分断リスクが低いと言われています。
59. DAOハック事件
解説
2016年にイーサリアム上で運営されていた初期のDAOが、スマートコントラクトの脆弱性を突かれ、大量のETHが不正に移転された事件です。この事件をきっかけにイーサリアムコミュニティはハードフォークを選択し、新チェーンが現在の「Ethereum(ETH)」、旧チェーンが「Ethereum Classic(ETC)」として存在することになりました。
60. メインネット(Mainnet)とテストネット(Testnet)
解説
- メインネット(Mainnet): 実際に仮想通貨やトークンの価値がある本番ネットワーク。
- テストネット(Testnet): 開発や実験、検証目的で使われるネットワーク。無料または低コストでトークン(テスト用)を入手できるため、DApps開発者やユーザーが安全にテストできる環境が提供されます。
61. オラクル(Oracle)
解説
ブロックチェーンの外部(オフチェーン)にある情報(価格データ、天候情報など)を、スマートコントラクトが利用できるようにする仕組みです。ブロックチェーンは内部のデータの整合性は保ちやすい一方で、外部情報を取得するには信頼できる中継役が必要になります。代表的なオラクルプロジェクトとしてChainlinkが挙げられます。
62. ステーブルコイン(Stablecoin)
解説
法定通貨(米ドルや円など)に価値を連動させることを目指す仮想通貨です。価格変動が激しいビットコインやアルトコインに比べ、安定した価値を持つため、送金や決済、DeFi取引の中間資産として利用されています。法定通貨担保型(USDT、USDCなど)、暗号資産担保型(DAIなど)、アルゴリズム型など、仕組みが複数存在します。
63. USDT(Tether)
解説
ステーブルコインの一種で、1USDT=1米ドルを目指して価値が維持されています。運営会社であるTether社が準備資産を裏付けとしていると説明していますが、準備金の透明性や監査体制などについて度々議論が起こっています。取引量が非常に大きく、仮想通貨マーケット全体に大きな影響力を持ちます。
64. USDC(USD Coin)
解説
Circle社とCoinbaseが共同で運営するドル連動型ステーブルコインです。1USDC=1米ドルを目標にし、米国の規制準拠を意識した運営が行われています。第三者監査を受けるなど、比較的透明性が高いとされ、ビジネス用途などでの利用も増えています。
65. DAI
解説
MakerDAOが発行・管理する暗号資産担保型ステーブルコインです。ETHなどの暗号資産をスマートコントラクトにロックすることでDAIが発行され、価格安定を保つために自動的に金利や担保率などが調整されます。アルゴリズム的な手法で価値を1ドル近辺に維持する、分散型ステーブルコインの代表例として知られています。
66. アルトコイン(Altcoin)
解説
ビットコイン以外のすべての仮想通貨を指す総称です。イーサリアムやリップル、ライトコインなど、主要なコインも含めて「代替的コイン(Alternative Coin)」と呼ばれています。技術的な特徴や用途は多岐にわたり、投資家にとっては「第二のビットコイン」を探す場として注目の対象となっています。
67. リップル(Ripple / XRP)
解説
Ripple社が開発する国際送金・決済システム、およびそのシステム上で使用される仮想通貨がXRPです。高速かつ低コストでの送金を目指し、銀行や金融機関向けのソリューションとして活用を推進しています。証券か否かを巡るSECとの裁判問題などがあり、市場の注目度が高い通貨の一つです。
68. ライトコイン(Litecoin / LTC)
解説
2011年にビットコインの改良版として誕生した仮想通貨です。ビットコインよりブロック生成速度が早く、より多くのコインの最大供給量を持ちます。長らく「デジタル銀」のように呼ばれ、ビットコインを「金」に例えるならライトコインは「銀」というポジションで知られてきました。
69. モネロ(Monero / XMR)
解説
プライバシー保護に特化した暗号資産です。リング署名やステルスアドレスなどの技術によって送金者や受取者の匿名性を高めます。そのためダークウェブなどで悪用されるケースも指摘されており、規制当局からの監視も強まっています。一方で合法的にプライバシーを確保したいユーザーにも支持されています。
70. Zキャッシュ(Zcash / ZEC)
解説
暗号学的手法「Zero-Knowledge Proof」を活用し、送金額や送金者・受取者のアドレスを秘匿できるプライバシーコインの一種です。透明性を確保した取引(透過アドレス)と秘匿性の高い取引(匿名アドレス)のどちらも選択可能なため、ユースケースに応じた使い分けが可能です。
71. パブリックチェーン(Public Blockchain)
解説
誰でも参加でき、取引を検証・承認できる完全にオープンなブロックチェーンです。ビットコインやイーサリアムが代表例で、ネットワークの透明性が高い反面、スケーラビリティや手数料の問題が課題となることがあります。オープンソースであり、誰でもノードを立ち上げてフルコピーを保持できる点が特徴です。
72. プライベートチェーン(Private Blockchain)
解説
企業や組織内で限定的にノードが許可される形で稼働するブロックチェーンです。情報の公開範囲やアクセス権を細かく制御できるため、機密性が求められるビジネス用途に向いています。しかし、一般的なパブリックチェーンに比べると分散性が低く、特定の管理者に依存する度合いが高くなる傾向があります。
73. コンソーシアムチェーン(Consortium Blockchain)
解説
複数の企業や組織が共同で管理・運用するブロックチェーンです。パブリックチェーンとプライベートチェーンの中間に位置し、参加ノードは限られますが、一つの中央管理者だけに依存しない形を目指します。金融機関や物流業界の企業連合が共同開発するケースなどで採用されることがあります。
74. ファントム(Fantom / FTM)
解説
高スループットと低手数料を特徴とする、DAG(Directed Acyclic Graph)に基づいたスマートコントラクトプラットフォームです。Lachesisと呼ばれる独自のコンセンサスメカニズムを採用しており、DeFi領域などで利用される機会が増えつつあるプロジェクトの一つです。
75. ソラナ(Solana / SOL)
解説
非常に高速なトランザクション処理能力を誇るレイヤー1ブロックチェーンです。Proof of History(PoH)とPoSを組み合わせ、数千~数万TPSを実現できるとされています。開発者が多く参入し、DeFiやNFT、ゲーム領域での活用が広がりましたが、たびたびネットワーク障害が発生してきた点などが課題です。
76. ポルカドット(Polkadot / DOT)
解説
異なるブロックチェーン同士の相互運用性(Interoperability)を実現するために開発されたプラットフォームです。メインとなるリレーチェーンと、目的別のパラチェーンを連携させる構造で、高い拡張性と柔軟性をもたらすことを目指しています。DOTトークンはステーキングやガバナンス投票にも使われます。
77. コスモス(Cosmos / ATOM)
解説
ブロックチェーン同士をつなぐ「インターネット・オブ・ブロックチェーン」を目標に掲げるプロジェクトです。Tendermint CoreというPoSベースのエンジンを活用し、Cosmos SDKを使って各種アプリケーション専用チェーンを構築できます。相互運用プロトコルIBC(Inter-Blockchain Communication)でチェーン間通信を可能にしています。
78. アバランチ(Avalanche / AVAX)
解説
高い処理速度と低コストを実現するレイヤー1ブロックチェーンの一つです。雪崩(Avalanche)の名を冠するコンセンサスプロトコルを採用し、数千TPSをサポートするとされています。独自のサブネット機能により、複数のブロックチェーンを並行して動かすことができ、DeFiやエンタープライズ用途での活用が進んでいます。
79. バイナンススマートチェーン(BSC / BNB Chain)
解説
大手取引所Binanceが開発・運営するブロックチェーンで、現在はBNB Chainと呼ばれます。イーサリアム互換の環境を提供しながら、手数料と高速性を特徴とし、多くのDAppsが展開されるようになりました。ただし中央集権的な運営が強いとも言われ、一定の批判や懸念も存在します。
80. NFTゲーム(Play-to-Earn / GameFi)
解説
NFTを活用したゲームで、アイテムやキャラクターがNFTとして所有できるため、ゲーム内資産に実際の価値が生まれます。さらに、ゲームプレイを通じて仮想通貨を稼ぐ仕組み(Play-to-Earn)が話題を集めています。代表例としてAxie Infinityなどがあり、新たな経済圏やビジネスモデルとして注目されています。
81. メタバース(Metaverse)
解説
仮想空間やオンライン上の3D空間で、人々がアバターを通じて交流したり、経済活動を行ったりする概念です。ブロックチェーンと組み合わせることで、仮想土地やアイテムをNFTとして所有し、相互運用性を持たせる試みが進んでいます。DecentralandやThe Sandboxなどが代表例です。
82. The Sandbox
解説
Ethereumベースのメタバースプラットフォームで、ユーザーはランド(LAND)と呼ばれる仮想土地を購入し、自由にゲームや体験を作って公開できます。独自トークンSANDを用いた経済圏が形成されており、企業や有名人がメタバース空間に参入する事例も増えています。
83. Decentraland
解説
Ethereum上で動作するメタバースプラットフォームの先駆け的存在です。MANAトークンとLAND NFTで構成される仮想世界を提供し、ユーザーは独自のコンテンツを土地に構築できます。アートやゲーム、イベントなど多様なアクティビティが行われており、仮想不動産が高値で取引されることもあります。
84. CBDC(Central Bank Digital Currency)
解説
中央銀行が発行するデジタル通貨です。民間の仮想通貨とは異なり、法的地位が政府や中央銀行によって裏付けられる点が特徴です。中国のデジタル人民元をはじめ、世界各国が研究・実証実験を進めています。従来の現金や銀行送金に変わる、新たな決済インフラとして注目されています。
85. ビットコインETF(Bitcoin ETF)
解説
ビットコインの価格に連動する上場投資信託(ETF)のことです。投資家は証券取引所で株式のように売買できるため、直接ビットコインを保有する必要がありません。カナダや欧州では複数のビットコインETFが存在しますが、米国では先物ベースのビットコインETFのみが承認されており、現物ETFの承認が注目されています。
86. エアドロップ(Airdrop)
解説
プロジェクトが自社トークンを無償でユーザーに配布するマーケティング手法です。新規プロジェクトが認知度向上やユーザーベースの拡大を狙う目的で行われることが多く、既存のトークン保有者や特定の条件を満たしたユーザーが対象となる場合もあります。レトロアクティブなエアドロップ(過去の利用実績に応じて付与)も増えています。
87. フォーモ(FOMO:Fear Of Missing Out)
解説
「流行や価格上昇の波に乗り遅れる恐怖」を指すネットスラングで、投資や仮想通貨市場でもしばしば使われます。周囲が儲けている話を聞いて焦りから高値掴みをしてしまう心理状態を表し、市場の過熱時にFOMOが多発することが相場のバブルを助長するとも言われています。
88. ダイヤモンドハンズ(Diamond Hands)
解説
相場が暴落しても決して売らずに堅く保有し続ける投資家を指すスラングです。GameStop騒動や仮想通貨バブル時に、コミュニティが「Diamond Hands」を称賛して持ち続ける姿勢を示した事例が有名です。逆にすぐに売ってしまう人を「Paper Hands」と呼ぶ場合があります。
89. テクニカル分析(Technical Analysis)
解説
価格チャートや取引量などの過去データから相場の動向やトレンドを予測する分析手法です。移動平均線やRSI、MACDなど、株式市場と同様の指標が仮想通貨市場でも活用されます。ただし仮想通貨はボラティリティが高く、テクニカル指標が効きにくい場合もあるため、ファンダメンタルズとの併用が推奨されます。
90. ファンダメンタルズ分析(Fundamental Analysis)
解説
プロジェクトの技術力やコミュニティの活発度、開発の進捗、提携状況などの実体的な要素を評価し、投資の判断に活かす分析手法です。仮想通貨の場合、ホワイトペーパーやGitHubのコミット履歴、SNSやフォーラムでの議論などが情報源となります。テクニカル分析だけでなく、ファンダメンタルズの理解も重要です。
91. ボラティリティ(Volatility)
解説
価格変動の大きさを示す指標です。仮想通貨は価格が急騰・急落しやすく、ボラティリティが高い傾向があります。投資家にとっては短期売買で大きなリターンを狙える反面、リスクも大きいという特徴があります。ポートフォリオ全体でのリスク管理が求められます。
92. マーケットキャップ(Market Cap / 時価総額)
解説
仮想通貨の場合、「発行枚数×1枚あたりの価格」で算出される指標で、市場規模を表します。時価総額が高いほど、そのコインやトークンの存在感が大きいと一般的にはみなされやすいですが、実際には流動性や分散状況、プロジェクトの実態なども見る必要があります。
93. ドミナンス(Dominance)
解説
ビットコインやイーサリアムなど、特定のコインが仮想通貨市場全体の時価総額に占める割合を指します。特にビットコインドミナンスは市場動向を知る上でよく注目される指標です。ビットコインドミナンスが下がると、アルトコインの人気が高まっている(アルトシーズン)と捉えられることもあります。
94. ガチホ(HODL)
解説
「Hold」のタイプミスから生まれた造語で、「長期保有し続ける」姿勢を示します。仮想通貨界隈では「ガチホ(本気でホールドするの意)」として日本語としても定着しています。短期的な値動きに左右されず、ビットコインなどを長期運用するホルダーが使うスラングです。
95. テザー砲
解説
USDT(Tether)が大量に新規発行されると市場への資金流入が増え、ビットコインなどの価格上昇を促すという文脈で、一部のトレーダーが「テザー砲が撃たれた」と表現します。実際には発行=価格上昇ではないとされていますが、市場心理に影響を与えることがあります。
96. フォークコイン(Fork Coin)
解説
ハードフォークによって旧チェーンと新チェーンに分裂した際に誕生する通貨の総称です。ビットコインキャッシュ(BCH)やビットコインSV(BSV)、イーサリアムクラシック(ETC)などが代表例です。保有していたビットコインやイーサリアムの枚数に応じて、新しく生まれたフォークコインを受け取れるケースがあります。
97. 半減期(Halving)
解説
ビットコインなどPoW通貨において、マイニング報酬が半分に減少するイベントです。ビットコインでは約4年ごとにブロック報酬が半減し、最終的な発行枚数が2100万枚に制限されます。半減期が訪れると供給量が減ることから、価格に上昇圧力がかかると期待される場合があり、過去の価格推移から相場のサイクルと関連付ける投資家もいます。
98. サトシ(Satoshi)
解説
ビットコインの最小単位で、1BTC=100,000,000サトシにあたります。また、ビットコインの創始者サトシ・ナカモトの名前でもあります。小額決済の際に使われる単位として認知されており、Lightning Networkなどの実用化とともに注目されることがあります。
99. ビットコインのピザ事件
解説
2010年5月22日、あるビットコインフォーラムユーザーが、1万BTCでピザ2枚を購入したのが世界初のビットコインによる実世界商品取引とされるエピソードです。当時は数ドルの価値でしたが、後に1万BTCが何億円相当にもなり、仮想通貨界隈では「ピザデー」として毎年話題になります。
100. マインドシェア(Mindshare)
解説
仮想通貨に限らず、消費者やコミュニティの意識・注目度・話題性をどれだけ集めているかを表す概念です。SNSでの言及数やコミュニティの活発度などがマインドシェアに影響し、相場にも連動する場合があります。投資家は価格だけでなくマインドシェアにも目を向けることで、プロジェクトの勢いを測ることができます。
まとめ
ここまで、仮想通貨・ブロックチェーンに関連する主要な100のキーワードを中心に、数行程度の解説をまとめました。仮想通貨は技術の進歩が速く、新しい用語やプロジェクトが次々と登場するため、常に最新情報を追いかけることが必要です。
- ビットコインなどの老舗コインの仕組みや歴史を学べば、「なぜビットコインが誕生し、これほどまでに注目されるのか」を理解できます。
- イーサリアムのスマートコントラクト技術やDeFi、NFTを学ぶことで、「ブロックチェーンがもたらす分散型サービスの可能性」を体験できます。
- レイヤー2ソリューションやクロスチェーン、スケーラビリティの課題などを知ると、「ブロックチェーンの現状の課題」と「これからの進化の方向性」が見えてきます。
また、投資家やトレーダーにとっては、テクニカル分析やファンダメンタルズ分析の双方を使いこなしつつ、市場心理を読むことも重要です。プロジェクトのホワイトペーパーやコミュニティ活動をチェックすることで、より深い理解を得ることができるでしょう。
仮想通貨の世界は分散的でグローバル、そして常に動きが激しい領域です。 この記事で紹介した用語が、みなさんの学習や投資活動の一助となれば幸いです。さらに興味を持ったキーワードがあれば、公式サイトや専門メディア、ホワイトペーパーなどをあわせてご確認ください。